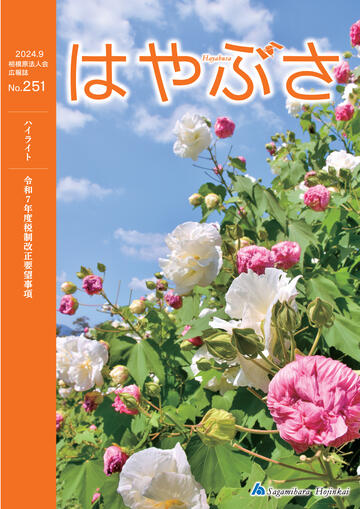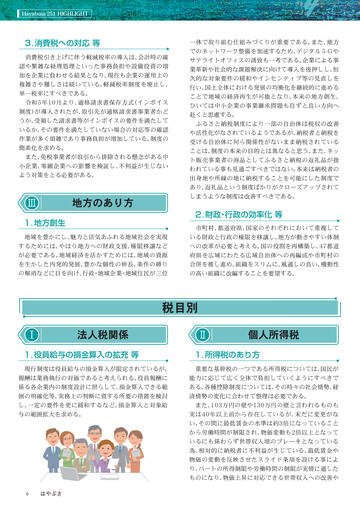はやぶさNo.251
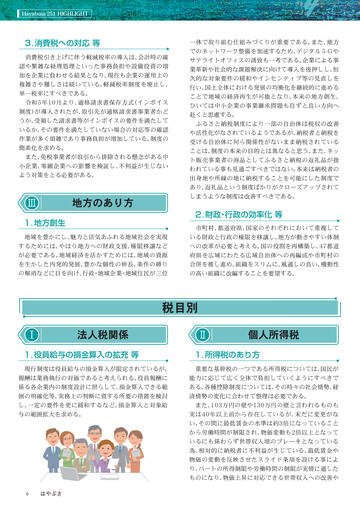
- ページ: 6
- Hayabusa 251 HIGHLIGHT
3.消費税への対応 等
消費税引き上げに伴う軽減税率の導入は、会計時の確
認や繁雑な経理処理といった事務負担や設備投資の増
加を企業に負わせる結果となり、現在も企業の運用上の
複雑さや難しさは続いている。軽減税率制度を廃止し、
単一税率にすべきである。
令和5年10月より、適格請求書保存方式(インボイス
制度)が導入されたが、取引先が適格請求書事業者かど
うか、受領した請求書等がインボイスの要件を満たして
いるか、その要件を満たしていない場合の対応等の確認
作業が多く煩雑であり事務負担が増加している。制度の
簡素化を求める。
また、免税事業者が取引から排除される懸念がある中
小企業、零細企業への影響を検証し、不利益が生じない
よう対策をとる必要がある。
Ⅲ
Ⅲ
地方のあり方
地方のあり方
一体で取り組む仕組みづくりが重要である。また、地方
でのネットワーク整備を加速するため、デジタル5Gや
サテライトオフィスの誘致も一考である。企業による事
業革新や社会的な課題解決に向けて導入を後押しし、恒
久的な対象要件の緩和やインセンティブ等の見直しを
行い、国土全体における発展の均衡化を継続的に進める
ことで地域の経済再生が可能となり、本来の地方創生、
ひいては中小企業の事業継承問題も自ずと良い方向へ
赴くと思慮する。
ふるさと納税制度により一部の自治体は税収の改善
や活性化がなされているようであるが、納税者と納税を
受ける自治体に何ら関係性がないまま納税されている
ことは、制度の本来の目的とは異なると思う。また、ネッ
ト販売事業者の商品としてふるさと納税の返礼品が扱
われている事も見過ごすべきではない。本来は納税者の
出身地や所縁の地に納税することを可能にした制度で
あり、返礼品という制度ばかりがクローズアップされて
しまうような制度は改善すべきである。
2.財政・行政の効率化 等
1.地方創生
地域を豊かにし、魅力と活気あふれる地域社会を実現
するためには、やはり地方への財政支援、権限移譲など
が必要である。地域経済を活かすためには、地域の資源
を生かした内発的発展、豊かな個性の伸長、条件の縛り
の解消などに目を向け、行政・地域企業・地域住民が三位
市町村、都道府県、国家のそれぞれにおいて重複して
いる財政と行政の権限を移譲し、地方が動きやすい体制
への改革が必要と考える。国の役割を再構築し、47都道
府県を広域にわたる広域自治体への再編成や市町村の
合併を推し進め、組織をスリムに、風通しの良い、機動性
の高い組織に改編することを要望する。
地方のあり方
法人税関係
1.役員給与の損金算入の拡充 等
現行制度は役員給与の損金算入が限定されているが、
報酬は業務執行の対価であると考えられる。役員報酬に
係る各企業内の制度設計に照らして、損金算入できる範
囲の明確化等、実務上の判断に資する所要の措置を検討
し、一定の要件を更に緩和するなど、損金算入と対象給
与の範囲拡大を求める。
Ⅲ
Ⅱ
時
る
入
べ
控
る
つ
税目別
Ⅰ
労
護
所
で
早
き
地方のあり方
個人所得税
家
措
1.所得税のあり方
重要な基幹税の一つである所得税については、国民が
能力に応じて広く全体で負担していくようにすべきで
ある。各種控除制度については、その時々の社会情勢、経
済情勢の変化に合わせて整理は必要である。
また、103万円の壁や130万円の壁と言われるものも
実は40年以上前から存在しているが、未だに変更がな
い。その間に最低賃金の水準は約3倍になっていること
を
ギ
り
与
考
から労働時間が制限され、物価変動も2倍以上となって
いるにも係わらず世帯収入増のブレーキとなっている
為、相対的に納税者に不利益が生じている。最低賃金や
物価の変動を反映させたスライド条項を設ける事によ
り、パートの所得制限や労働時間の制限が実情に適した
ものになり、物価上昇に対応できる世帯収入への改善や
が
�
- ▲TOP