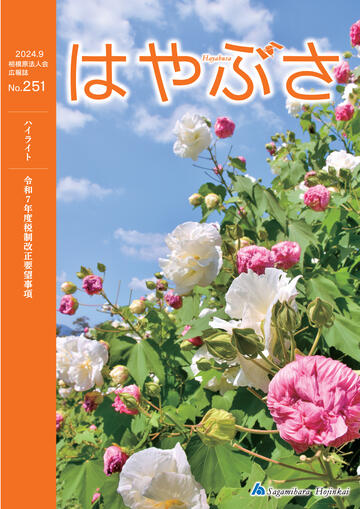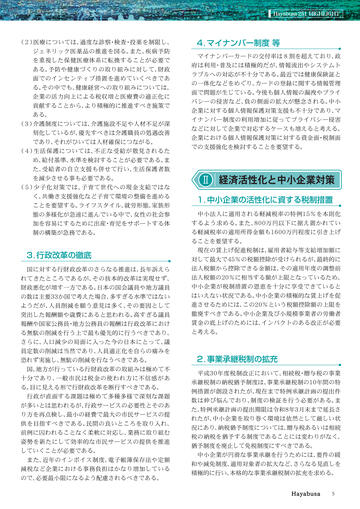はやぶさNo.251
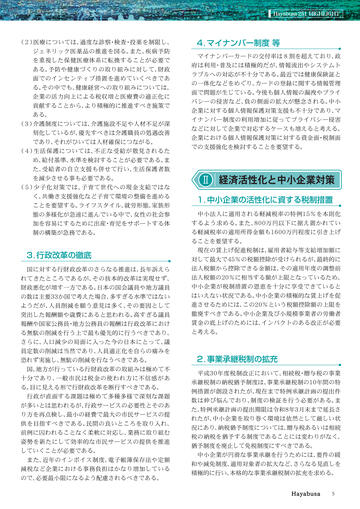
- ページ: 5
- 展
改
Hayabusa 251 HIGHLIGHT
(2)医療については、過度な診察・検査・投薬を制限し、
ジェネリック医薬品の推進を図る。また、疾病予防
を重視した保健医療体系に転換することが必要で
ある。予防や健康づくりの取り組みに対して、財政
面でのインセンティブ措置を進めていくべきであ
る。その中でも、健康経営への取り組みについては、
企業の活力向上による税収増と医療費の適正化に
貢献することから、より積極的に推進すべき施策で
ある。
(3)介護制度については、介護施設不足や人材不足が深
刻化しているが、優先すべきは介護職員の処遇改善
であり、それがひいては人材確保につながる。
(4)生活保護については、不正な受給が散見されるた
め、給付基準、水準を検討することが必要である。ま
た、受給者の自立支援も併せて行い、生活保護者数
を減少させる事も必要である。
(5)少子化対策では、子育て世代への現金支給ではな
く、共働き支援強化など子育て環境の整備を進める
ことを要望する。ライフスタイル、就労形態、家族形
態の多様化が急速に進んでいる中で、女性の社会参
加を容易にするために出産・育児をサポートする体
制の構築が急務である。
主
し
況
が
政
税
の
に
の
給
中
あ
ッ
る
3.行政改革の徹底
国に対する行財政改革のさらなる推進は、長年訴えら
れてきたところであるが、その抜本的改革は実現せず、
財政悪化が増す一方である。日本の国会議員や地方議員
の数は主要33か国で考えた場合、多すぎる水準ではない
ようだが、人員削減を願う意見は多く、その要因として
突出した報酬額や歳費にあると思われる。高すぎる議員
報酬や国家公務員・地方公務員の報酬は行政改革におけ
る無駄の削減を行う上で最も優先的に行うべきであり、
さらに、人口減少の局面に入った今の日本にとって、議
員定数の削減は当然であり、人員適正化を自らの痛みを
恐れず実施し、無駄の削減を行なうべきである。
国、地方が行っている行財政改革の取組みは極めて不
十分であり、一般市民は税金の使われ方に不信感があ
る。目に見える形で行財政改革を断行すべきである。
行政が直面する課題は極めて多種多様で深刻な課題
が多いとは思われるが、行政サービスの必要性とそのあ
り方を再点検し、最小の経費で最大の市民サービスの提
供を目指すべきである。民間の良いところを取り入れ、
前例に囚われることなく柔軟に対応し、業務に取り組む
姿勢を新たにして効率的な市民サービスの提供を推進
していくことが必要である。
また、近年のインボイス制度、電子帳簿保存法や定額
減税など企業における事務負担はかなり増加している
ので、必要最小限になるよう配慮されるべきである。
4.マイナンバー制度 等
マイナンバーカードの交付率は8割を超えており、政
府は利用・普及には積極的だが、情報流出やシステムト
ラブルへの対応が不十分である。最近では健康保険証と
の一体化などをめぐり、カードの登録に関する情報管理
面で問題が生じている。今後も個人情報の漏洩やプライ
バシーの侵害など、負の側面の拡大が懸念される。中小
企業に対する個人情報保護対策支援も不十分であり、マ
イナンバー制度の利用増加に従ってプライバシー侵害
などに対して企業で対応するケースも増えると考える。
企業における個人情報保護対策に対する資金面・税制面
での支援強化を検討することを要望する。
Ⅱ 経済活性化と中小企業対策
1.中小企業の活性化に資する税制措置
中小法人に適用される軽減税率の特例15%を本則化
するよう求める。また、800万円以下に据え置かれてい
る軽減税率の適用所得金額も1600万円程度に引き上げ
ることを要望する。
現在の賃上げ促進税制は、雇用者給与等支給増加額に
対して最大で45%の税額控除が受けられるが、最終的に
法人税額から控除できる金額は、その適用年度の調整前
法人税額の20%に相当する額が上限となっているため、
中小企業が税制措置の恩恵を十分に享受できていると
はいえない状況である。中小企業の積極的な賃上げを促
進させるためには、この20%という税額控除額の上限を
撤廃すべきである。中小企業及び小規模事業者の労働者
賃金の底上げのためには、インパクトのある改正が必要
と考える。
2.事業承継税制の拡充
平成30年度税制改正において、相続税・贈与税の事業
承継税制の納税猶予制度は、
事業承継税制の10年間の特
例措置が創設されたが、
現在まで特例承継計画の提出件
数は伸び悩んでおり、制度の検証を行う必要がある。ま
た、
特例承継計画の提出期限は令和8年3月末まで延長さ
れたが、
中小企業を取り巻く環境は依然として厳しい状
況にあり、
納税猶予制度については、
贈与税あるいは相続
税の納税を猶予する制度であることには変わりがなく、
猶予制度を廃止して免税制度にすべきである。
中小企業が円滑な事業承継を行うためには、
要件の緩
和や減免制度、
適用対象者の拡大など、
さらなる見直しを
積極的に行い、
本格的な事業承継税制の拡充を求める。
�
- ▲TOP