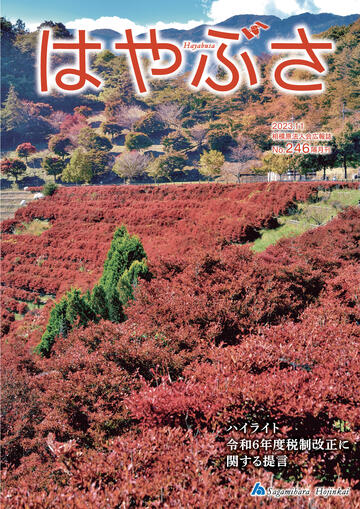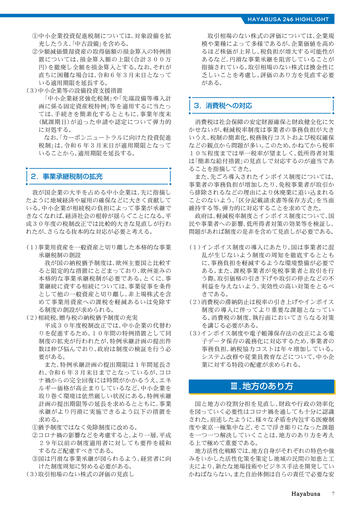はやぶさNo.246
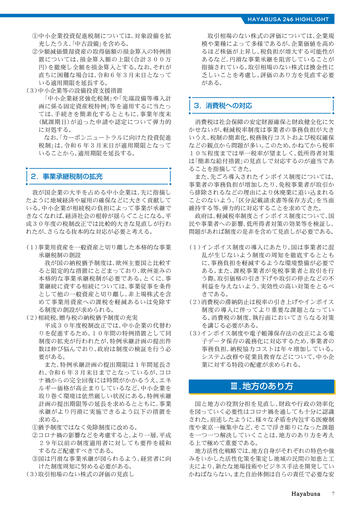
- ページ: 7
- Hayabusa 246 HIGHLIGHT
①中小企業投資促進税制については、対象設備を拡
充したうえ、
「中古設備」を含める。
②少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措
置については、損金算入額の上限(合計300万
円)を撤廃し全額を損金算入とする。なお、それが
直ちに困難な場合は、令和6年3月末日となって
いる適用期限を延長する。
(3)中小企業等の設備投資支援措置
「中小企業経営強化税制」や「先端設備等導入計
画に係る固定資産税特例」等を適用するに当たっ
ては、手続きを簡素化するとともに、事業年度末
(賦課期日)が迫った申請や認定について弾力的
に対処する。
なお、
「カーボンニュートラルに向けた投資促進
税制」は、令和6年3月末日が適用期限となって
いることから、適用期限を延長する。
2.事業承継税制の拡充
我が国企業の大半を占める中小企業は、先に指摘し
たように地域経済や雇用の確保などに大きく貢献して
いる。中小企業が相続税の負担によって事業が承継で
きなくなれば、経済社会の根幹が揺らぐことになる。平
成30年度の税制改正では比較的大きな見直しが行わ
れたが、さらなる抜本的な対応が必要と考える。
(1)事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事業
承継税制の創設
我が国の納税猶予制度は、欧州主要国と比較す
ると限定的な措置にとどまっており、欧州並みの
本格的な事業承継税制が必要である。とくに、事
業継続に資する相続については、事業従事を条件
として他の一般資産と切り離し、非上場株式を含
めて事業用資産への課税を軽減あるいは免除す
る制度の創設が求められる。
(2)相続税、贈与税の納税猶予制度の充実
平成30年度税制改正では、中小企業の代替わ
りを促進するため、10年間の特例措置として同
制度の拡充が行われたが、特例承継計画の提出件
数は伸び悩んでおり、政府は制度の検証を行う必
要がある。
また、特例承継計画の提出期限は1年間延長さ
れ、令和6年3月末日までとなっているが、コロ
ナ禍からの完全回復には時間がかかるうえ、エネ
ルギー価格が高止まりしているなど、中小企業を
取り巻く環境は依然厳しい状況にある。特例承継
計画の提出期限等の延長を求めるとともに、事業
承継がより円滑に実施できるよう以下の措置を
求める。
①猶予制度ではなく免除制度に改める。
②コロナ禍の影響などを考慮すると、より一層、平成
29年以前の制度適用者に対しても要件を緩和
するなど配慮すべきである。
③国は円滑な事業承継が図られるよう、経営者に向
けた制度周知に努める必要がある。
(3)取引相場のない株式の評価の見直し
取引相場のない株式の評価については、企業規
模や業種によって多様であるが、企業価値を高め
るほど株価が上昇し、税負担が増大する可能性が
あるなど、円滑な事業承継を阻害していることが
指摘されている。取引相場のない株式は換金性に
乏しいことを考慮し、評価のあり方を見直す必要
がある。
3.消費税への対応
消費税は社会保障の安定財源確保と財政健全化に欠
かせないが、軽減税率制度は事業者の事務負担が大き
いうえ、税制の簡素化、税務執行コストおよび税収確保
などの観点から問題が多い。このため、かねてから税率
10%程度までは単一税率が望ましく、低所得者対策
は「簡素な給付措置」の見直しで対応するのが適当であ
ることを指摘してきた。
また、先ごろ導入されたインボイス制度については、
事業者の事務負担が増加したり、免税事業者が取引か
ら排除されるなどの理由により休廃業に追い込まれる
ことのないよう、
「区分記載請求書等保存方式」を当面
維持する等、弾力的に対応することを求めてきた。
政府は、軽減税率制度とインボイス制度について、国
民や事業者への影響、低所得者対策の効果等を検証し、
問題があれば制度の是非を含めて見直しが必要である。
(1)インボイス制度の導入にあたり、国は事業者に混
乱が生じないよう制度の周知を徹底するととも
に、事務負担を軽減するような環境整備が必要で
ある。また、課税事業者が免税事業者と取引を行
う際、取引価格の引き下げや取引の停止などの不
利益を与えないよう、実効性の高い対策をとるべ
きである。
(2)消費税の滞納防止は税率の引き上げやインボイス
制度の導入に伴ってより重要な課題となってい
る。消費税の制度、執行面においてさらなる対策
を講じる必要がある。
(3)インボイス制度や電子帳簿保存法の改正による電
子データ保存の義務化に対応するため、事業者の
事務負担、納税協力コストは年々増加している。
システム改修や従業員教育などについて、中小企
業に対する特段の配慮が求められる。
Ⅲ.地方のあり方
国と地方の役割分担を見直し、財政や行政の効率化
を図っていく必要性はコロナ禍を通しても十分に認識
された。前述したように、様々な矛盾を内包する医療制
度や東京一極集中など、そこで浮き彫りになった課題
を一つ一つ解決していくことは、地方のあり方を考え
る上で極めて重要である。
地方活性化戦略では、地方自身がそれぞれの特色や強
みをいかした活性化策を策定し地域の民間の知恵と工
夫により、新たな地場技術やビジネス手法を開発してい
かねばならない。また自治体側は自らの責任で必要な安
�
- ▲TOP