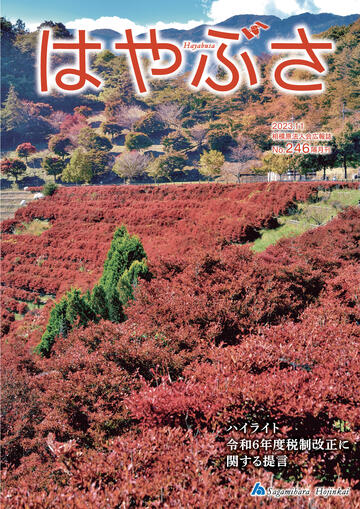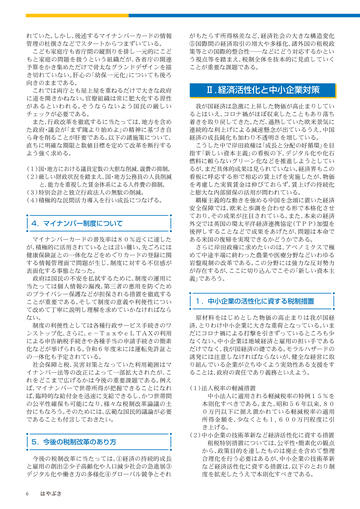はやぶさNo.246
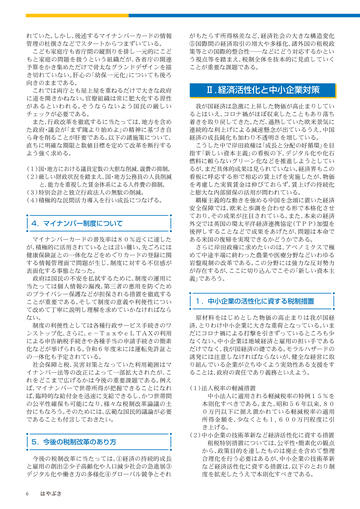
- ページ: 6
- れていた。しかし、後述するマイナンバーカードの情報
管理の杜撰さなどでスタートからつまずいている。
こども家庭庁も省庁間の縦割りを排し一元的にこど
もと家庭の問題を扱うという組織だが、各省庁の関連
予算をかき集めただけで骨太なグランドデザインを描
き切れていない。肝心の「幼保一元化」についても後ろ
向きのままである。
これでは両庁とも屋上屋を重ねるだけで大きな政府
に道を開きかねない。官僚組織は常に肥大化する習性
があるといわれる。そうならないよう国民の厳しい
チェックが必要である。
また、行政改革を徹底するに当たっては、地方を含め
た政府・議会が「まず隗より始めよ」の精神に基づき自
ら身を削ることが肝要である。以下の諸施策について、
直ちに明確な期限と数値目標を定めて改革を断行する
よう強く求める。
(1)国・地方における議員定数の大胆な削減、歳費の抑制。
(2)厳しい財政状況を踏まえ、国・地方公務員の人員削減
と、能力を重視した賃金体系による人件費の抑制。
(3)特別会計と独立行政法人の無駄の削減。
(4)積極的な民間活力導入を行い成長につなげる。
4.マイナンバー制度について
マイナンバーカードの普及率は80%近くに達した
が、積極的に活用されているとは言い難い。先ごろには
健康保険証との一体化などをめぐりカードの登録に関
する情報管理面で問題が生じ、制度に対する不信感が
表面化する事態となった。
政府は国民の不安を払拭するために、制度の運用に
当たっては個人情報の漏洩、第三者の悪用を防ぐため
のプライバシー保護などが担保される措置を徹底する
ことが重要である。そして制度の意義や利便性につい
て改めて丁寧に説明し理解を求めていかなければなら
ない。
制度の利便性としては各種行政サービス手続きのワ
ンストップ化、さらに、e−TaxやeLTAXの利用
による申告納税手続きや各種手当の申請手続きの簡素
化などが挙げられる。令和6年度末には運転免許証と
の一体化も予定されている。
社会保障と税、災害対策となっていた利用範囲はマ
イナンバー法等の改正によって一部拡大されたが、こ
れをどこまで広げるかは今後の重要課題である。例え
ば、マイナンバーで世帯所得が把握できることになれ
ば、臨時的な給付金を迅速に支給できるし、かつ世帯間
の公平性確保も可能になり、様々な税制改革論議の土
台にもなろう。そのためには、広範な国民的議論が必要
であることも付言しておきたい。
5.今後の税制改革のあり方
今後の税制改革に当たっては、①経済の持続的成長
と雇用の創出②少子高齢化や人口減少社会の急進展③
デジタル化や働き方の多様化④グローバル競争とそれ
がもたらす所得格差など、経済社会の大きな構造変化
⑤国際間の経済取引の増大や多様化、諸外国の租税政
策等との国際的整合性――などにどう対応するかとい
う視点等を踏まえ、税制全体を抜本的に見直していく
ことが重要な課題である。
Ⅱ.経済活性化と中小企業対策
我が国経済は急激に上昇した物価が高止まりしてい
るとはいえ、コロナ禍がほぼ収束したこともあり落ち
着きを取り戻してきた。ただ、過熱していた欧米景気に
連続的な利上げによる減速懸念が出ているうえ、中国
経済の成長鈍化も加わり不透明さを増している。
こうした中で岸田政権は「成長と分配の好循環」を目
指す「新しい資本主義」の看板の下、デジタル化や化石
燃料に頼らないグリーン化などを推進しようとしてい
るが、まだ具体的成果は見られていない。経済界もこの
看板に呼応する形で相応の賃上げを実施したが、物価
を考慮した実質賃金は伸びておらず、賃上げの持続化
と膨大な内部留保の活用が問われている。
覇権主義的な動きを強める中国を念頭に置いた経済
安全保障では、欧米と歩調を合わせる形で本格化させ
ており、その成果が注目されている。また、本来の経済
外交では英国の環太平洋経済連携協定(TPP)加盟を
後押しすることなどで成果をあげたが、問題は本命で
ある米国の復帰を実現できるかどうかである。
さらに岸田政権に求めたいのは、アベノミクスで極
めて中途半端に終わった農業や医療分野などいわゆる
岩盤規制の改革である。この分野には強力な反対勢力
が存在するが、ここに切り込んでこその「新しい資本主
義」であろう。
1.中小企業の活性化に資する税制措置
原材料をはじめとした物価の高止まりは我が国経
済、とりわけ中小企業に大きな重荷となっている。いま
だにコロナ禍による打撃を引きずっているところも少
なくない。中小企業は地域経済と雇用の担い手である
だけでなく、我が国経済の礎である。モラルハザードの
誘発には注意しなければならないが、健全な経営に取
り組んでいる企業が立ちゆくよう実効性ある支援をす
ることは、政府の責任であり義務といえよう。
(1)法人税率の軽減措置
中小法人に適用される軽減税率の特例15%を
本則化すべきである。また、昭和56年以来、80
0万円以下に据え置かれている軽減税率の適用
所得金額を、少なくとも1,600万円程度に引
き上げる。
(2)中小企業の技術革新など経済活性化に資する措置
租税特別措置については、公平性・簡素化の観点
から、政策目的を達したものは廃止を含めて整理
合理化を行う必要はあるが、中小企業の技術革新
など経済活性化に資する措置は、以下のとおり制
度を拡充したうえで本則化すべきである。
�
- ▲TOP