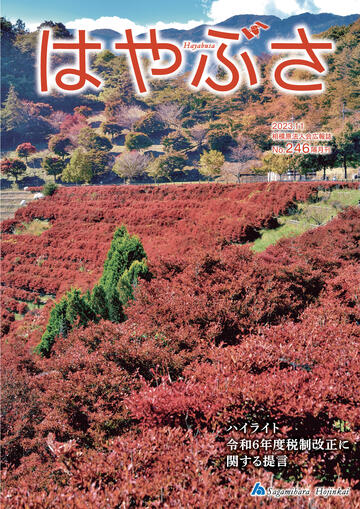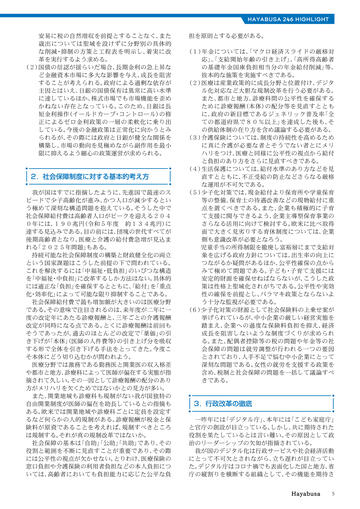はやぶさNo.246
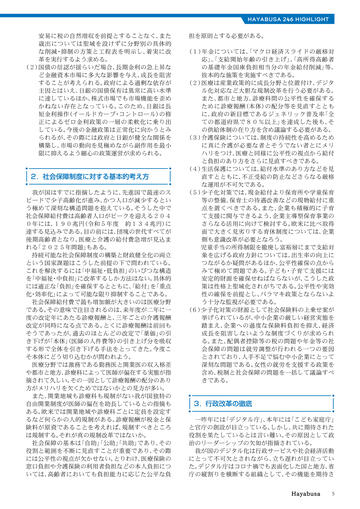
- ページ: 5
- Hayabusa 246 HIGHLIGHT
安易に税の自然増収を前提とすることなく、また
歳出については聖域を設けずに分野別の具体的
な削減・抑制の方策と工程表を明示し、着実に改
革を実行するよう求める。
(2)国債の信認が揺らいだ場合、長期金利の急上昇な
ど金融資本市場に多大な影響を与え、成長を阻害
することが考えられる。政府による過剰な依存が
主因とはいえ、日銀の国債保有は異常に高い水準
に達しているほか、株式市場でも市場機能を歪め
かねない存在となっている。このため、日銀は長
短金利操作(イールドカーブ・コントロール)の修
正によるゼロ金利政策の一層の柔軟化に乗り出
している。今後の金融政策は正常化に向かうとみ
られるが、その際には政府と日銀が健全な関係を
構築し、市場の動向を見極めながら副作用を最小
限に抑えるよう細心の政策運営が求められる。
2.社会保障制度に対する基本的考え方
我が国はすでに指摘したように、先進国で最速のス
ピードで少子高齢化が進み、かつ人口が減少するとい
う極めて深刻な構造問題を抱えている。そうした中で
社会保障給付費は高齢者人口がピークを迎える204
0年には、190兆円(令和5年度 約134兆円)に
達する見込みである。目の前には、団塊の世代すべてが
後期高齢者となり、医療と介護の給付費急増が見込ま
れる「2025年問題」もある。
持続可能な社会保障制度の構築と財政健全化の両立
という国家課題はこうした前提の下で問われている。
これを解決するには「中福祉・低負担」のいびつな構造
を「中福祉・中負担」に改革するしか方法はない。具体的
には適正な「負担」を確保するとともに、
「給付」を「重点
化・効率化」によって可能な限り抑制することである。
社会保障給付費で最も増加額が大きいのは医療分野
である。その意味で注目されるのは、来年度が二年に一
度の改定年にあたる診療報酬と、三年ごとの介護報酬
改定が同時になる点である。とくに診療報酬は前回も
そうであったが、過去のほとんどの改定で「薬価」の引
き下げが「本体」
(医師の人件費等)の引き上げ分を吸収
する形で全体を引き下げる手法をとってきた。今度こ
そ本体にどう切り込むかが問われよう。
医療分野では激務である勤務医と開業医の収入格差
や都市と地方、診療科によって医師が偏在する実態が指
摘されて久しい。その一因として診療報酬の配分のあり
方がメリハリを欠くためではないかとの見方が多い。
また、開業地域も診療科も規制がない我が国独特の
自由開業制度が医師の偏在を助長しているとの指摘も
ある。欧米では開業地域や診療科ごとに定員を設定す
るなど何らかの人的規制がある。診療報酬が税金と保
険料が原資であることを考えれば、規制すべきところ
は規制する。それが真の規制改革ではないか。
社会保障の基本は「自助」
「公助」
「共助」であり、その
役割と範囲を不断に見直すことが重要であり、その際
には公平性の視点が欠かせない。とりわけ、医療保険の
窓口負担や介護保険の利用者負担などの本人負担につ
いては、高齢者においても負担能力に応じた公平な負
担を原則とする必要がある。
(1)年金については、
「 マクロ経済スライドの厳格対
応」、
「 支給開始年齢の引き上げ」、
「 高所得高齢者
の基礎年金国庫負担相当分の年金給付削減」等、
抜本的な施策を実施すべきである。
(2)医療は産業政策的に成長分野と位置付け、デジタ
ル化対応など大胆な規制改革を行う必要がある。
また、都市と地方、診療科間の公平性を確保する
ために診療報酬(本体)の配分等を見直すととも
に、政府の新目標であるジェネリック普及率「全
ての都道府県で80%以上」を達成した後も、そ
の供給体制の在り方を含め議論する必要がある。
(3)介護保険については、制度の持続性を高めるため
に真に介護が必要な者とそうでない者とにメリ
ハリをつけ、医療と同様に公平性の視点から給付
と負担のあり方をさらに見直すべきである。
(4)生活保護については、給付水準のあり方などを見
直すとともに、不正受給の防止などさらなる厳格
な運用が不可欠である。
(5)少子化対策では、現金給付より保育所や学童保育
等の整備、保育士の待遇改善などの現物給付に重
点を置くべきである。また、企業も積極的に子育
て支援に関与できるよう、企業主導型保育事業の
さらなる活用に向けて検討する。欧米に比べ取得
面で大きく見劣りする育休制度については、企業
側も意識改革が必要となろう。
児童手当の所得制限を撤廃し富裕層にまで支給対
象を広げる政府方針については、出生率の向上に
つながるか疑問があるほか、公平性確保の点から
みて極めて問題である。子ども・子育て支援には
安定的財源を確保せねばならないが、こうした政
策は性格上聖域化されがちである。公平性や実効
性の確保を前提とし、バラマキ政策とならないよ
う十分な監視が必要である。
(6)少子化対策の財源として社会保険料の上乗せ案が
挙げられているが、中小企業の厳しい経営実態を
踏まえ、企業への過度な保険料負担を抑え、経済
成長を阻害しないような制度づくりが求められ
る。また、配偶者控除等の税の問題や年金等の社
会保障の問題は就労調整が行われる一つの要因
とされており、人手不足で悩む中小企業にとって
深刻な問題である。女性の就労を支援する政策を
含め、税制と社会保障の問題を一括して議論すべ
きである。
3.行政改革の徹底
一昨年には「デジタル庁」、本年には「こども家庭庁」
と官庁の創設が目立っている。しかし、共に期待された
役割を果たしているとは言い難い。その原因として政
治のリーダーシップの欠如が指摘されている。
我が国のデジタル化は行政サービスや社会経済活動
にとって不可欠とされながら、立ち遅れが目立ってい
た。デジタル庁はコロナ禍でも表面化した国と地方、省
庁の縦割りを横断する組織として、その機能を期待さ
�
- ▲TOP